被災建築物応急危険度判定
被災建築物応急危険度判定制度のご紹介

先の兵庫県南部地震のおりに、全国の地方公共団体等の支援を受けて、日本で初めて本格的に実施された、「被災建築物応急危険度判定」とは、地震直後の余 震等による二次災害を防止する目的で被災建築物を調査し、その結果を罹災者に下図のような標識の掲示で知らせて注意を促すことを言い、この調査を行う資格者を「被災建築物応急危険度判定士」と言います。
色々な職場に働く建築技術者の皆様が、応急危険度判定技術を習得し、地震時の判定業務を担える資格を備えておくことは、一般市民の信頼に応え、建築技術 者の社会的地位の向上に寄与するものであることをご理解されまして、一人でも多くの建築技術者の方々が判定士資格を取得されますようお奨めいたします。
福岡県では、資格者養成講習会が平成7年度から実施されており、すでに2,200名を超える建築技術者の方々が判定士として登録されています。
しかしながら、万一の地震を考えますと、さらに多くの判定士を養成する必要がありますので、毎年応急危険度判定技術を習得していただくための講習会を、 福岡県・北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市から委託を受けて開催いたしております。
一人でも多くの建築技術者の方が受講・登録して下さいますことをお待ちしております。
福岡県応急危険度判定士資格取得について
福岡県の「被災建築物応急危険度判定士」資格は、講習会を年に1度開催し、講習を修了した方からの申し出を受けた福岡県知事が、登録を行うことにより認定されます。
認定を受けた方には、「被災建築物応急危険度判定士認定証」が交付されます。
なお、この資格者は、5年毎に更新をしていただくことになっております。
(福岡県における登録の事務は、県の委託を受けた、建築住宅センターが窓口になって行っております)
講習会の概要
開催日時・会場
| 福岡会場 | 令和8年1月14日(水)13:30~16:30 | 福岡県中小企業振興センター301会議室 |
| 北九州会場 | 令和8年1月28日(水)13:30~16:30 | パークサイドビル9階大会議室 |
| WEB講習会 | 配信日:令和8年2月17日(火)~2月28日(土)※WEB講習会ご希望の方はコチラをご覧ください。 | |
申込方法
下記受付フォームよりお申し込みください。
◎受講受付フォーム
受講資格・対象者
- 建築士(建築士法第2条第1項)または特定建築物調査員で福岡県内に在住か在勤している方
- 建築行政に携わる公務員(建築に関する実務経験が3年以上)
- 令和7年度末(2026年3月31日)更新対象者(登録番号の先頭の数字2桁が20の方)又は期限切れ等で再受講を希望する者
(※更新者の講習会受講は更新要件ではございません)
新規登録手続きについて
応急危険度判定士講習会を受講された方は、下記書類をご確認いただき、ご郵送またはWEBにてお手続きをお願いいたします。
事務局にて受講確認後に登録証を発行いたします。
WEB手続きはコチラ
※お手続きの時期によっては、発行までに時間を要する場合がございます。
| 新規手続き書類 |
|
|---|
他都道府県との資格の相互認証
福岡県で資格を取得された方が、他の都道府県に転居された場合、移転先の都道府県知事に認定申請手続きを行うことで再度講習を受けることなく資格が認定されます。
また、他の都道府県で登録されていた方で福岡県に転入された方は、下記書類をご確認いただき、福岡県での登録手続きをお願いいたします。
※お手続きの時期によっては、発行までに時間を要する場合がございます。
| 県外からの方用登録書類 |
|
|---|
更新手続きについて
応急危険度判定士の登録は5年ごとの更新が必要です。更新時期が近づきましたら、登録された自宅住所へ更新を発送いたします。 更新書類を紛失された方、未更新の方も下記書類をご確認いただき、更新手続きをお願いいたします。
WEB手続きはコチラ
※お手続きの時期によっては、発行までに時間を要する場合がございます。
| 更新手続書類 |
|
|---|
登録事項の変更手続きについて
応急危険度判定士の登録内容(住所、勤務先、氏名、連絡先など)に変更があった場合は、下記の書類をご確認のうえ、ご郵送またはWEBにてお手続きをお願いいたします。
WEB手続きはコチラ
| 登録事項変更届出書 |
|
|---|
メールアドレス情報の登録のお願い
緊急時の派遣依頼や重要なお知らせをより迅速にお届けするため、R4年度よりメールアドレスの登録をお願いしております。
下記アドレスより登録をお願いいたします。
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=ecp9Bnko
応急危険度判定広報誌 OQ通信
応急危険度判定広報誌 OQ通信第28号が発刊されました。 (令和7年12月24日発刊)
・被災建築物応急危険度判定マニュアルの改訂について
・令和6年能登半島地震における実施本部及び支援本部の動きについて
(令和6年能登半島地震の応急危険度判定の記録より抜粋)
・派遣準備体制について
| OQ通信 第28号 |
|
|---|
判定士制度をさらに詳しく知りたい方は
- (一財)日本建築防災協会のホームページをご覧ください。
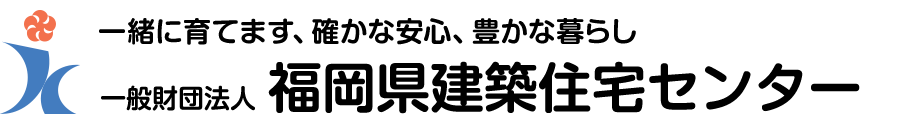
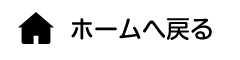
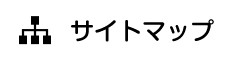







 消費者の方
消費者の方 事業者の方
事業者の方