構造計算適合性判定業務
構造計算適合性判定の状況
当センターでは、お引受から質疑事項のご連絡まで5営業日以内、適合判定通知書の交付まで2週間以内を目標に業務を行っております。現在の判定状況については、下記をご参照ください。
- 現在の判定状況(PDF)(毎週更新 令和7年12月22日時点)
- 受付後、構造計算適合性判定待ち、或いは判定中の棟数 1件( 1棟)
- 設計者からの補正・追加説明書待ち、或いは確認中の棟数 25件(31棟)
- 判定受付件数等、総判定件数及び平均判定日数等の状況(PDF)(毎月更新 令和7年11月末日時点)
構造計算適合性判定業務について
- 確認申請を行う場合は、建築主は建築確認とは別に構造計算適合性判定を指定構造計算適合判定機関等に直接申請することになります。(平成27年6月1日以降)
- 国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
- 建築基準法第20条の規定により、既存不適格である建築物に増改築を行う際に、許容応力度等計算、保有水平耐力計算及び限界耐力計算を行う場合、新築と同様に構造計算適合性判定の対象となります。
- エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部分毎に、異なる構造計算の方法の適用や、構造計算適合性判定の要否の判断が可能となります。
参考:国土交通省 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について
※ 詳しくは建築主事又は指定確認検査機関へお尋ねください。
A:業務規程及び約款
判定機関として行う判定業務の実施について、必要な事項を定めています。
※令和7年2月28日付で「構造計算適合性判定業務規程」及び「構造計算適合性判定業務約款」の改定を行いました。
※改定後の規程及び約款は、令和7年4月1日より施行されます。
| 構造計算適合性判定業務規程(~R7.3.31) |
|
|---|---|
| 構造計算適合性判定業務約款(~R7.3.31) |
|
| 機関省令第31条の9の2で定める掲示及び公衆の閲覧事項 |
|
| 【改定後の業務規程等】※R7.4.1以降有効の規程等 |
|
| 構造計算適合性判定業務規程(R7.4.1~) | |
| 構造計算適合性判定業務約款(R7.4.1~) |
|
B:判定を要する建築物
構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、建築基準法第20条第2号において、
- 地階を除く階数が4以上であるもの又は高さが16mを超える木造の建築物
- 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
- 高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
等を規定しています。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定しています。
C:当センターの判定業務の範囲
福岡県内に建築する建築物で、構造計算適合性判定を要するもののうち、限界耐力計算、時刻歴応答解析などの性能規定による構造計算方法を除くものを対象として判定を行います。
詳しくは下記のとおりです。
法第6条の3第1項及び法第18条第5項の規定に基づき構造計算適合性判定を要する建築物で、次のいずれにも該当しない建築物
1 限界耐力計算又は、これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による建築物
2 特殊な工法等の採用により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物
3 指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)第3第3号の規定により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物
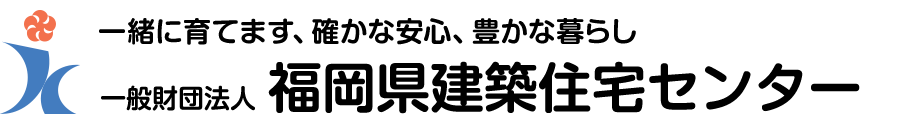
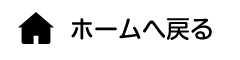
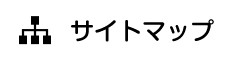







 消費者の方
消費者の方 事業者の方
事業者の方